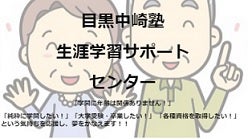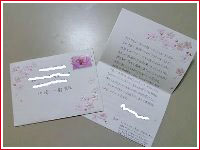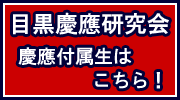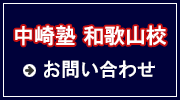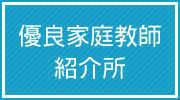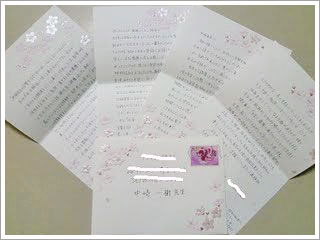| |
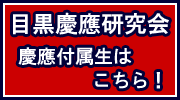

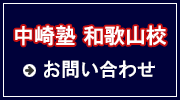
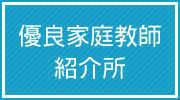
中崎塾シニアサポート 【メッセージ】 シニアの生涯学習をサポートしてゆきます! |
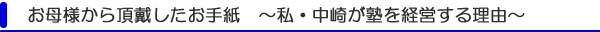 |
|
このお手紙を頂戴することが出来たから、今、自分は塾の経営を進めてゆくことができています。
迷ったり、弱気になった時には、このお手紙を読み直しています。
そうすると、段々と前に進む力が湧いてきます。
そんな大切なお手紙なのですが、お母様からの掲載のご許可をいただきましたので、内容を皆様にご紹介させて頂きたいと思います。
|
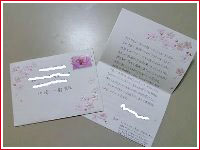 |
|
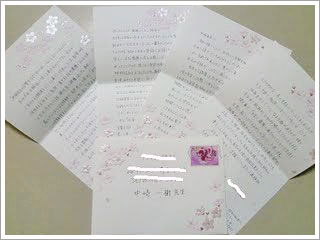
|
|
振り返ればあっという間の期間でした。
お忙しい合間を縫って息子の勉強を見ていただきどうもありがとうございました。
受験を目前に控えた11月、塾には行かせていても、とても不安な時期でした。知名度は高く、合格実績を主張している塾に通わせていたものの、6年生になってから成績がどんどんと落ちていきました。親子共に元気を失い、実際には合格はほど遠い気持ちでいました。
そんな中で、中崎先生とお会いしました。
最後の望みとしていた志望校に過去問で10点ほど足りませんでした。本当に残りの3ヶ月で合格まで実力を高めることができるのか、焦りと失望でいっぱいでした。しかし、中崎先生は最初のお電話で「10点足りないのなら合格するんじゃないかな。」とおっしゃってくださいました。「可能性が低い学校であっても何校か受ければ合格する可能性は上がります。」と客観的な数値を示して説明してくれました。経験豊富な先生がおっしゃって下さったという心強さに救われた気持ちになりました。
そして、私と息子の心のよりどころとなりました。
それまで出会ってきた先生は、どの先生も、私が準備しておいた息子がミスした問題を黙って見てくださるだけでした。そして時間になればすぐに帰ってしまいます。しかし、中崎先生はまず息子の現状についてじっくり聞いて下さり、合格のために今何をすることが先決か非常に適切なご意見をくださいました。
合格に向けて効率を考えた場合、時間を割いてでも取り組むべき事柄と、優先的にこなす必要はない事柄があるとは認識していました。しかし、限りある時間の中で、その取捨選択が本当に難しく焦りがつのっていました。
そんな中で、中崎先生は今まで出会ってきた先生とは違い、取捨選択について的確にご指示くださいました。多数の生徒を見ていらした実績、そこからくる自信を感じました。とても心強かったです。
先生は「授業は、マンツーマンか多くても1:3の授業形式で。」という信念を貫かれています。大手の塾では、個人個人の苦手な箇所は違うにも関わらず、画一的な授業しか受ける事が出来ません。大手の塾とは違い、息子ととことん向き合い、きめ細かく指導して頂いたことが最後のひと伸びにつながったと思っています。
また、先生はすぐに解き方を教えてしまわず、徹底的に自分自身で考えさせる事を実践してくださいました。その結果、息子も次第に、「人の力を借りて解いた」のではなく、「自らが解いた」と自信を持てるようになっていったと実感しています。
先生のご指導のおかげで、息子は自ら考え自ら答えを導き出すことの面白さに気づいたようでした。
誰の力も借りることができない入試会場で、最終的に合格を掴み取ることができたのは、自ら考え自ら答えを導き出すことを息子なりに全うしてくれたからだと思っています。これからも自ら考え自ら答えを導き出すことを続けて欲しいと願っています。
受験の目前はかなりストレスを受ける状況でした。中崎先生は、息子の今の自宅学習のやり方や、私のやり場のない不安感等を時間を惜しむことなく聞いて下さり、アドバイスをくださいました。
一日の時間の使い方を手帳につける事などもご提案くださり、勉強以外のことも沢山学ぶことが出来ました。
息子が合格可能性が低かった学校に合格出来たのは、最後に中崎先生に出会えたお陰だと思います。
また、礼儀作法を大切にし、寺子屋のような、勉強したい子供が集まる環境を作ろうと邁進されている中崎先生をこれからも応援したいと思います。
私は息子が中崎先生のようになってくれたらいいと願っています。中崎先生の「人間性」は、本当に素晴らしいです。
いよいよあと数週間で受験という直前期、この最もナーバスになる時期に、心の底から「自分はこの時期何をしていたか。」と思い出して下さりました。そして、「今、自分がやりたいと思う勉強をすればいいんじゃないですかね。」とおっしゃって下さった時、私たち親子の中に、受験への「覚悟」が生まれました。
また、これも出来ない、あれもダメだ、と不安材料を抱え込む私達に「今はそれはやらなくていい。」とおっしゃって下さった時、本当に救われました。
才能もお人柄も素晴らしい先生に出会えて幸運でした。
とりとめのない長いお手紙になってしまいました。また、中学で勉強につまづいたときは、どうか息子を宜しくお願いいたします。
怠けぐせがあるので、時々先生から知的関心をそそられる話を聞くことで「大学で慶應に再チャレンジ」という気持ちを思い起こしてくれるのではないかと思っています。
二度と繰り返すことができない大切な受験生活を、中崎先生とご一緒できたことで有効に過ごすことができました。
一生懸命に息子を見てくださって本当にどうもありがとうございました。
先生のお陰で私と息子は受験を乗り越えることができました。
先生のお陰で合格することができました。
本当に、本当に有難うございました。
どうか今後もご活躍ください。
まずは御礼まで。
|
|
受験勉強や試験勉強を通じて、子供達が幸せに生きていってくれる種を植えていきたいと思っています。もちろん、試験に合格することやテストで良い点数を取ること自体もとても大切な目標です。ただやはり、ひとりの人間として幸せな未来を過ごしていって欲しいと願っています。
頂戴したお手紙の内容にまだまだ自分は到達していない未熟者なのですが、いずれはお母様が書いてくださったような人間になれるように日々邁進しています。
子供に教えられ、気づかされ、子供と共に悩み、共に勉強する。
そういう素晴らしい環境をくださっているすべての皆様に感謝しています。
|
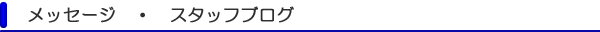 |
 慶應大学医学部生(当塾講師)よりの講座推薦文章
慶應大学医学部生(当塾講師)よりの講座推薦文章
こんにちは、慶應大学医学部2年生のFと言います。
今回は、私の経験から、小学生の頃から高校受験の勉強をする意義についてお話ししようと思います。
私は、小学生5年生の頃から神奈川県の高校受験塾に通っていました。
元々は中学受験をするつもりだったのですが、体が弱かったため、断念し、やりどころのないモチベーションを、高校受験の勉強に向けよう思いました。
しかし勉強と言っても、小学生の頃は多くとも一日1時間、中学生になっても一日2時間程度、というのが私の勉強の特徴でした。それでも成績は順調に伸び続け、無事慶應義塾高校に合格することができました。
この勉強の仕方で成功した秘訣としては、部活動や遊びと両立することができた、ということに尽きると思います。
集中して詰め込むことも大切なのですが、モチベーションを保ち継続的に勉強をすることが、基本的ですが、中学生にとって最も重要な勉強法です。
集中して詰め込むことが大切と言いましたが、勉強においてむしろそれが一番早くて効率的なやり方です。
しかし、それは簡単にできることではありません、高校生なら可能かもしれませんが、中学生には限界があります。
だからこそ、部活動や遊びと両立して、楽しみながら受験をすることが、良い成果にもつながると思うのです。
私は小学生の頃受けたいと思っていた中学よりレベルも高く素晴らしい高校に合格することができて、結果的に良い方向に進むことができました。小学生の皆さんには中学受験も良いですが、
長い目で高校受験に挑戦するという手段を、私はお勧めしたいと思います。
|
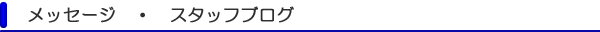 |
|
 慶應大学医学部A君より皆さまへ
慶應大学医学部A君より皆さまへ
突然ですが私は、人間の1つの大きな特徴が「習慣」だと思っています。
人は習慣に従って日々を生きています。
朝起きて、顔を洗って、歯を磨いて、朝食を食べて、学校に行って…
習慣は国や文化、更には家族や個人で大枠が有りますが、人は皆それぞれ何かしらの習慣を持って生きています。
人はそれぞれの習慣を軸にして、自分の生活を形作っているのです。
「習慣は第二の天性なり」と言う格言があります。
これは、習慣は天賦の才能や元来の性格と同じくらいに、人の性質に影響を与えるという意味です。
例えば私たちの健康や肉体は、食生活という一種の習慣に大きく影響されます。
食習慣に影響された健康や肉体は、精神状態にも影響します。
精神状態は、私たちの後天的な性格に影響します。
このように習慣とは、人間の生き方に重要な意味を持ちます。
しかし習慣は才能と異なり、自分で律することができるのです。
確かに、一度身に付いた習慣を変更したり、止めたり、もしくは新しい習慣を自らの生活の中に組み込むことは相当なエネルギーを要します。
ですが、逆に言えば1度忍耐を用いれば、良い方向に自分の習慣を変えることは出来るのです。
私は中学まで全く勉強する習慣の無い人間でした。
高校に入り、将来の目標を考えた時に大学受験という現実に立ち向かわなくてはならないことに気付きました。
そのためには勉強習慣をつけなくてはならないと思い立ち、とりあえず興味のあった「数学」と「化学」という科目について、まず1週間とにかく机に向かって1日二時間勉強してみようと考え実行してみました。
毎日部活から帰り、机の周りの漫画やゲームなどの誘惑を振り切って1週間半ば負荷をかけて勉強した所、8日目からは「意外と」すんなりと勉強に向かうことができました。(もちろん目標があったこともモチベーションを保てた一つの要因になっているのですが)
1度身に付いた習慣は取り戻すのが楽になり、何日か勉強を休んだ時もやる気が戻った時にスッと机に戻ることができました。
家でも学校でも塾でも、勉強の習慣がつけられない人はとりあえず無理してでも何日か続けて勉強してみてはどうでしょうか?
それがあなたの第二の天性になるかもしれません。
|
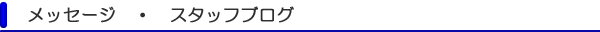 |
|
 慶應大学医学部B君より皆さまへ
慶應大学医学部B君より皆さまへ
(自己紹介文)
慶應義塾大学医学部1年生。
小学校4年生から日能研(京都の桂校、烏丸校、兵庫の西宮北口校に所属)に通って勉強し、中学受験を経験し、京都の洛南高等学校附属中学校に合格、進学。
中高一貫校なので高校受験は経験せず、洛南高等学校に進学。高校2年から河合塾(京都校)に通って大学受験勉強をし、慶應義塾大学医学部と京都大学理学部に現役合格、2012年4月、慶應義塾大学医学部に進学。
小学校時代は算数、理科、社会が得意で、国語が苦手でした。中学校時代に数学が一旦苦手になるも、高校に進学してから再び得意になりました。高校2年で化学がわからず、学校の授業についていけなくなるも、3年に重点的に努力した結果、最得意科目になりました。
物理はずっと得意教科です。英語はスピードが遅いものの、不得意ではなくむしろ得意なほうでした。現代文は相変わらず苦手ですが、古文・漢文は得意です。センター試験では社会科目として地理を受験しました。
趣味はスポーツ・音楽などです。小学校では陸上部(長距離)、中学校では水泳部、高校ではバレーボール部に所属し、現在、慶應医学部バレーボール部に所属しています。その他に、地域のクラブや学校の休み時間では、野球、バスケットボール、スキー、柔道(初段取得)なども経験しています。音楽では、J-POPやJ-ROCKが好きで、中学3年から始めたギターで、高校1年、2年時に文化祭でバンド演奏もしました。
性格は明るくお人好しですが、お人好しが重度であることと強い好奇心ゆえに色んなことをしたがって欲張る結果、時間がなくなって自分で自分を苦しめてしまうことが多いです。
教職を目指したこともあり、人に勉強を教えるのがとても好きです。同級生に教えることもよくあります。精一杯指導させていただきたいと思うので、よろしくお願いします。
::::::::::::::::::::::::
(メッセージ記事・・・4回連載分の1回目)
こんにちは。
慶應医学部1年のものです
今日は、私が今まで得意として勉強してきた、数学についてお話させていただこうと思います。
数学とは、特殊な科目です。才能が有ればそれだけで解けるようになったりせず、かといって、努力さえすれば伸びるとも言い切れない、なんだか扱いの難しい科目だと思います。社会系科目のように、ひたすら努力して暗記すればどうにかなる科目とはちょっと違います。(こんなことを言うと社会の先生に怒られそうですが。笑)
数学を身に付ける際のパターンはこのような感じです。
基本事項の確認・理解→基本事項から導かれる公式の理解(・暗記)→公式を用いて問題を解く練習→実践的な問題を解く練習→応用
中学・高校・大学で学ぶ数学はいずれもこの段階を踏んでいる、と私は思います。
では、数学が得意な人と苦手な人で、どのように差がつくのか、私の思うところを述べたいと思います。
まず才能に左右されるものは何なのでしょうか。
私の考えでは、理解能力、これだけです。いままで自分を含め、周囲の人の数学への取り組み、能力、成績を観察、分析している限りでは、そう思います。
理解能力で差がつくのは、新しい分野を学ぶとき、問題の内容を把握するとき、それだけだと思います。
あとは何で左右されるのか。
意欲と経験だと思います。
公式の暗記は、努力して覚える以上に、数学では、経験しながら覚えるものが多いです。
問題を解く練習の量が、意欲に左右されるものなのは言うまでもありません。
応用力は、なかなか身に付けるのが難しいので、一言で済ませず、少し詳しく考えてみたいと思います。
まず、最近の大学入試問題では、初見で解けるほどの応用力を求めていない問題がたくさんあります。これらは、類似問題を練習し、経験していて、解き方を知っているかを確かめられるような意図で出題されています。こういった問題は、実際の入試では“絶対に落としてはいけない問題”で、あまり差は付きません。
では、実際に差がつく問題は、どのような問題なのかというと、上記のような定番問題に、ひとひねりを加えた、少し難しい問題です。しかし、それはあくまで“ひとひねり”であって、かなり難しい問題ではないので、頑張れば解ける問題なのです。頑張っても解けないような問題は、誰も解けないので(解けても数学ヲタクのような超人だけ)、差がつく問題にはなりません。
その“ひとひねり”を解く応用力を身に付けるためにひつようなものは、経験に伴う柔軟な思考法と、数学に対する感動、であると私は信じています。
経験に伴う柔軟な思考法とは、数学でいう引き出しの多さ、ということです。何が言いたいかというと、差がつく問題は、様々な分野が組み合わさってできているので、一つの解き方にこだわらず、様々な方向から多角的なアプローチができることが、問題を解く重要なカギとなります。
数学に対する感動は、意欲を向上させ、応用力を伸ばす、素晴らしいものだと思います。自分でわからなかった問題を先生や友人が教えてくれる解き方に感動する。長い時間、自分が悩みに悩んだ末に解けたときの達成感のような感動。
私は、数学を学ぶ皆さんに、この感動をできるだけ多く経験してほしいと願っています。それはきっと、数学を好きになり、数学を得意教科とするために役立つものだと信じています。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
|
|
|
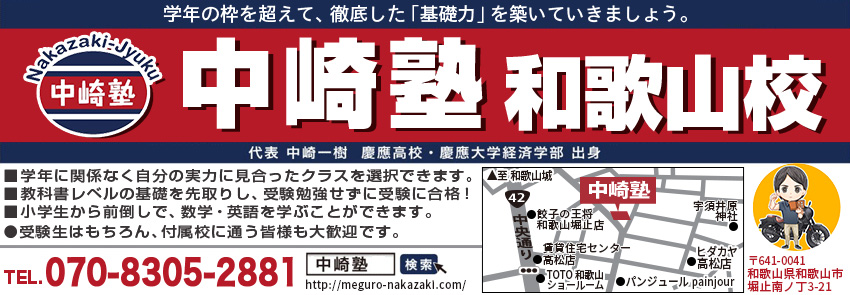
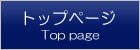
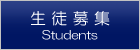
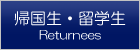
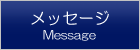


 中崎塾・スタッフブログとメッセージ
中崎塾・スタッフブログとメッセージ